副院長
整形外科部長


当科が扱う疾患分野は「運動器」です。「運動器」とは自分の意思でもって動かせるからだの部分を指し、神経・骨・軟骨・筋肉・靭帯などで構成されています。これらが怪我や病気、加齢に伴う変性などで障害されると、立つ・歩く・手を動かすといったヒトとしての基本動作に重大な悪影響を及ぼします。
また、整形外科は、損なわれた運動機能の回復・改善をめざす診療科であり、赤ちゃんからお年寄りまで、男女の別なくきわめて多岐にわたる疾患が対象となっています。的確な診断のもと、患者さんの目線に立って治療を進めてまいります。しかしながら、前述のように、「運動器」は自分が命令しなければ動きません。言い換えれば、何もせずにじっとしていて機能が回復することはないのです。患者さんご自身のご理解とご協力をお願いいたします。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 藤岡 池上 |
池上 大神 |
大橋 | 中瀨 出射 |
中瀨 大神 |
小田/リウマチ (※1) 大西/肩(※2) 非常勤担当医/一般外来(※3) |
| 午後 (予約診) |
長谷 | 池上 | 小池 大橋 |
中瀨 | 出射 |
※1 5日,19日
※2 12日,26日
※3 受付時間11時まで
骨折・靭帯損傷などの外傷性疾患、変形性関節症・変形性脊椎症・脊柱管狭窄症などの変性疾患、骨壊死、外反拇趾、手術の必要な関節リウマチなど
ギプスなどでおこなう保存治療と、必要な場合はプレートや髄内釘などを用いた手術療法を行います。
進行の程度・年齢・職業などにより、手術以外の方法(保存治療)や適切なタイミングで手術療法を行います。骨切り術やさまざまな人工関節手術や骨移植術などがあります。
わが国では世界に類を見ない勢いで人口の高齢化が進行中です。そして、骨折・変形性関節症・変形性脊椎症・脊椎圧迫骨折といった整形外科疾患が、要介護の原因の実に四分の一以上を占めるようになっています。脳卒中・心臓病・認知症といった病気より多くなっているのです。両方の膝が痛いとか、腰も痛くて脚もしびれて動きにくいなど原因となる箇所がいくつもあったり、最近転びやすくなったと感じている方も少なくないはずです。「ロコモ」とはこういった「要介護の危険性が高まった状態」のことを指します。政府と日本整形外科学会が一体となって介護予防に向けての啓蒙活動を行っており、簡単なトレーニング(ロコトレ)によって効果を上げつつあります。整形外科では、原因を探って治療することにより、長く元気で動けるからだ作りのお手伝いをしています。
| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 骨折観血的手術 | 271 | 280 | 237 | 225 | 239 | 259 |
| 関節鏡関連手術 | 13 | 15 | 10 | 8 | 3 | 9 |
| 人工股関節関連手術 | 14 | 17 | 16 | 9 | 35 | 22 |
| 人工膝関節関連手術 | 11 | 18 | 14 | 11 | 19 | 11 |
| 大腿骨人工骨頭挿入術 | 42 | 48 | 40 | 40 | 48 | 54 |
| 脊椎脊髄外科手術 | 172 | 168 | 31 | 57 | 61 | 203 |
| その他 | 151 | 148 | 261 | 238 | 244 | 143 |
| 合計 | 664 | 694 | 609 | 588 | 649 | 701 |
現在日本全国で骨粗鬆症患者は1300万人を超えると言われています。
骨粗鬆症により背骨の骨折(脊椎圧迫骨折)、手首の骨折(橈骨遠位端骨折)、太ももの付け根の骨折(大腿骨近位部骨折)などが生じやすくなります。
また、一度このような骨折を起こすと次々と骨折をくり返すことがあります。連鎖する骨折を防ぐために骨粗鬆症を早期に発見して、できるだけ早めに治療を行うことが重要です。
当院の骨粗鬆症リエゾンサービス(OLS)はメディカルスタッフの連携によるチーム医療を行っています。
骨の強さを骨密度検査で測定し、場合によっては血液検査やレントゲン検査を行います。
近年、様々な骨粗鬆症治療薬が開発されています。薬物治療により骨密度増加や骨質改善効果が得られることで、骨折を防いで健康寿命が延伸することが期待されています。
また転倒予防のためバランス能力を評価して筋力訓練を行い、バランスのとれた食事の栄養指導を行います。
*女性、閉経・・・骨の代謝を調節する女性ホルモンのエストロゲンが閉経により減少し、骨粗鬆症の危険性が高まります。
*加齢・・・骨量は20歳代で最大になり、40歳代後半から徐々に減少します。
*体型・・・小柄な人、やせていて筋肉の少ない人は骨が弱くなりがちです。
*遺伝・・・特に母親が太ももの付け根の骨折(大腿骨近位部骨折)を生じた場合は注意が必要です。
*喫煙、飲酒・・・カルシウムの吸収が低下します。
*他の病気、薬剤の影響・・・関節リウマチ、糖尿病、慢性腎臓病、副甲状腺機能亢進症、ステロイド。
*食生活のみだれ、運動不足

骨粗鬆症リエゾンサービス(OLS)チーム
当院では2023年にOLSチームを立ち上げました。骨粗鬆症認定医、看護師、薬剤師、理学療法士、管理栄養士、医療事務など多職種が連携し、各々の専門性を活かして骨粗鬆症治療を行い、骨折予防に取り組んでいます。
検査内容
骨密度検査(せぼね、太ももの骨など)
レントゲン検査(せぼね、太ももの骨など)
血液検査(骨がつくられたり、こわされたりする骨の代謝のバランス、カルシウム、ビタミンDなどを調べます)
*検査結果をもとに治療が必要な場合は薬物治療、運動指導、栄養指導、生活習慣のアドバイスを行います。



副院長
整形外科部長
京都府立医科大学大学院医学研究科 医学博士
日本整形外科学会専門医
日本リハビリテーション医学会認定臨床医
日本リハビリテーション医学会専門医
日本リハビリテーション医学会指導医
京都府立医科大学大学院医学研究科 運動器機能再生外科学 臨床教授
京都府立医科大学大学院医学研究科 リハビリテーション医学 臨床教授
日本股関節学会 評議員
日本リハビリテーション医学会 代議員
日本リハビリテーション医学会近畿地方会 幹事
京都府リハビリテーション教育センター運営委員

副部長
日本整形外科学会専門医
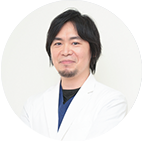
脊椎脊髄外科センター
センター長
京都府立医科大学医学博士
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医
日本脊椎脊髄病学会認定脊椎脊髄外科指導医
脊椎脊髄外科専門医
日本骨粗鬆症学会認定医

脊椎脊髄外科センター
名誉センター長
京都府立医科大学医学博士
日本整形外科学会専門医
日整会脊椎脊髄病医
日本脊椎脊髄病学会指導医
日本脊椎脊髄神経手術手技学会理事
日本側弯症学会会員
日本リウマチ関節外科学会会員
脊椎脊髄外科、リハビリテーション医学京都府立医科大学整形外科で27年間脊椎クリニックを担当

医長
日本整形外科学会専門医

医員
日本整形外科学会専門医

医員

理事長
日本整形外科学会専門医
日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医
日本整形外科学会認定スポーツ医
日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医